
一人読書会の世界名作シリーズは、
『カラマーゾフの兄弟』(ドストエフスキー)(連載・計29回)
と読んできて、次は、
を読んでみたいと思う。
書き出しの
「幸せな家庭はどれもみな似ているが、不幸な家庭にはそれぞれの不幸の形がある」
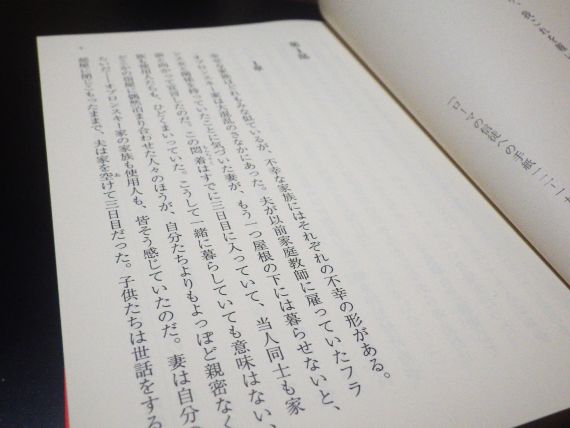
という一文が有名な、トルストイの代表作のひとつで、
トルストイの最高傑作として、『戦争と平和』より上位に置く人も多い。
私は学生時代に一度読んでいるが、
もう半世紀も昔のことなので、すっかり忘れている。
2013年に、映画『アンナ・カレーニナ』も見ているが、
主演した(私の好きな)キーラ・ナイトレイに見惚れてしまって、
こちらもあまり憶えていない。(笑)

……ということで、半世紀ぶりに『アンナ・カレーニナ』を読みたいと思う。
現在、翻訳本としては、
木村彰一訳『アンナ・カレーニナ』筑摩書房(世界文学全集37, 38)、1970年
中村融訳『アンナ・カレーニナ』岩波文庫(上中下)、改版1989年
木村浩訳『アンナ・カレーニナ』新潮文庫(上中下)、再改版2012年
北御門二郎訳『アンナ・カレーニナ』東海大学出版会(上下)、新版2000年
望月哲男訳『アンナ・カレーニナ』光文社古典新訳文庫(全4巻)、2008年
などがあるが、
今回は、名訳の誉れ高い望月哲男訳で読んでみたいと思う。
光文社古典新訳文庫版の『カラマーゾフの兄弟』が読みやすかったし、
同じ光文社古典新訳文庫版『アンナ・カレーニナ』なら間違いはないだろう。
それに、望月哲男の新訳『アンナ・カレーニナ』は、
「ロシア文学国際翻訳者センターコンクール」で最優秀翻訳賞を受賞している。
折り紙付きなのだ。

……では、読み始めよう。
第1部、1章
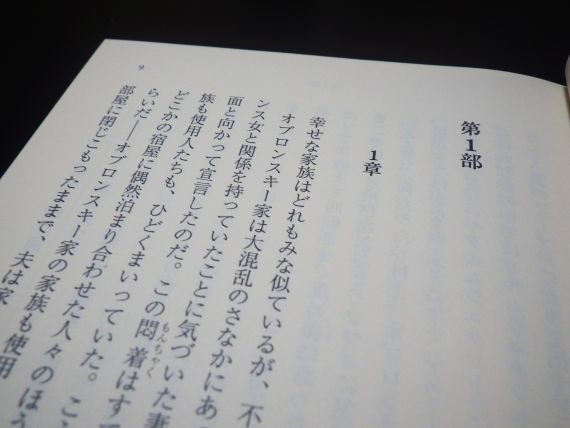
幸せな家庭はどれもみな似ているが、不幸な家庭にはそれぞれの不幸の形がある。オブロンスキー家は大混乱のさなかにあった。夫が以前家庭教師に雇っていたフランス女と関係を持っていたことに気づいた妻が、もう一つ屋根の下には暮らせないと、面と向かって宣言したのだ。妻は自分の部屋に閉じこもったままで、夫は家を空けて三日目だった。夫のオブロンスキー侯爵(社交界での愛称はスティーヴァ。アンナ・カレーニナの兄である)は午前8時に目を覚まし、自分が妻の寝室ではなく書斎に寝ていたことを思い出し、その理由も思い出した。観劇に出かけた彼が帰宅すると、妻のドリーが、寝室の中で、あの不吉な、すべてを明かすメモを手にしたままじっと坐り込み、恐怖と絶望と怒りのこもった目でこちらを見つめていたのだった。「これは何? これは?」妻はメモを示して問いかけた。そのとき彼は、自分の意志とは一切関係なく、まったく不本意にも、ふといつもながらの優しい、それゆえに間の抜けた笑みを浮かべたのだった。その笑顔を見ると、妻のドリーは激しやすい気性に任せてきつい言葉でさんざんまくし立てると、ぷいと部屋を飛び出して、以来、妻は夫に会おうとしないのである。
2章
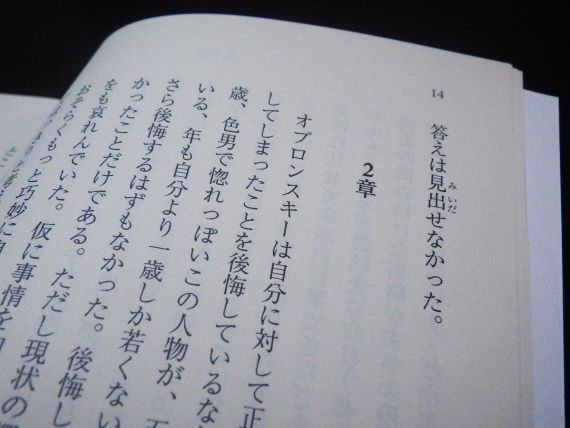
5人の子供の母であり、年も自分より1歳しか若くない妻に、34歳の色男で惚れっぽいオブロンスキーは関心を失っていた。浮気に関して後悔はしておらず、後悔しているのは、もっとうまく妻に隠し事ができなかったということだけであった。彼が呼び鈴を鳴らすと、長いなじみの従僕マトヴェイが入ってきた。オブロンスキーが「マトヴェイ、妹のアンナが明日やってくるぞ」と言うと、マトヴェイが「では、二階のお部屋をご用意しましょうか?」と訊いてきたので、「妻に伝えて、どこがいいか聞くがいい」と返事した。妻に探りをいれるつもりであることを察したマトヴェイがドリーに訊きに行くが、「ご主人さまのよろしいように」との素っ気ない返事であった。ばあやのマトリョーナがやってきて、「ご主人さま、おいでになってもう一度お謝りになってください。奥さまは大変苦しまれて、見ていて辛うございます」と言ったが、オブロンスキーは、「わかったから戻ってなさい」と言って、部屋着を脱ぎ捨て、着替えを始めた。
3章
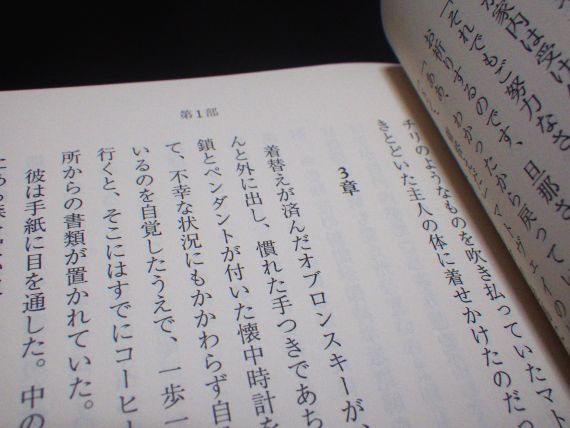
着替えを済ませたオブロンスキーが食堂へ行くと、すでにコーヒーが彼を待っていて、その脇には手紙類と勤務先の役所からの書類が置かれていた。手紙と書類に目を通した後、オブロンスキーは新聞を読み始めた。購読しているのはリベラルな新聞だった。リベラル派はロシアでは何ひとつうまくいっていないと主張してきたが、実際、オブロンスキーは負債だらけで、どうしようもないほどの金欠病だった。彼がリベラルな新聞を好むのは、ちょうど食後に葉巻をふかすのを好むのと同じで、読んでいると頭にもやっと軽い霧がかかるような感じがするのが好ましかったのである。二人の子供の声が聞こえたので、彼は子供たちを呼び、娘の方に「ママはどうしている?」と訊いた。「ママ? 起きているわよ」と娘が答えた。「ということは、またまた一晩中眠れなかったのだな」と彼は思った。請願者の相談事に対処した後、オブロンスキーは、妻の寝室へと通じるもうひとつのドアを開けた。
4章
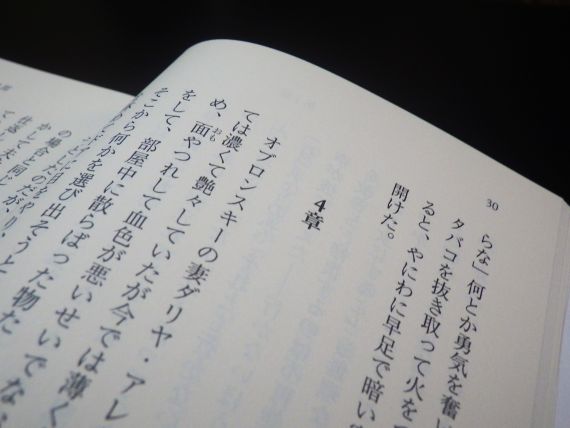
オブロンスキーの妻ダリア・アレクサンドロヴナ(ドリー)は、面やつれして血色が悪いせいでなおさら大きくむき出したように見える怯えた目をして、部屋中に散らばった物たちに囲まれて、開いた洋服ダンスの前に立っていた。彼女は、実家へ帰るかどうかまだ決断がつかないでいた。口では夫を捨てるつもりだと言いながら、それは不可能だと感じていた。衣服を選び出しては、出て行くふりをしていたのだった。「ドリー!」「何の御用ですの?」「アンナが今日やってくるそうだ」「わたしに関係ないでしょう? お相手することはできません!」「ドリー、言えるのはただひとつ、許してくれ、許してほしい……考えてもみてくれ、いったいこれまでの九年間の生活で贖えないだろうか、ほんのつかの間の、つかの間の浮気心を……」「出て行って、ここから出て行って! そんな浮気心だの汚らわしい関係だのの話はもうたくさん!」。ドリーはドアをバタンと閉めて出て行った。
5章
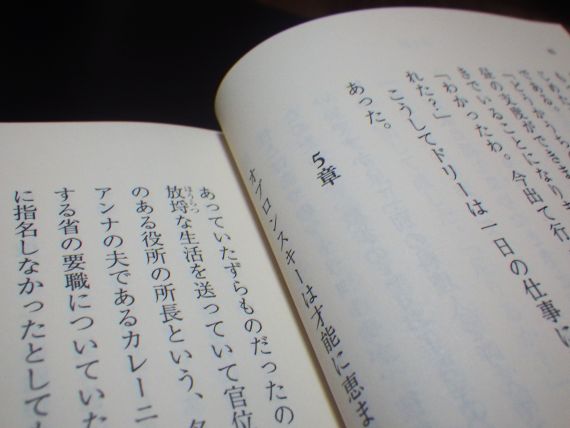
オブロンスキーは、学校の勉強はよくできたが、怠け癖があって、卒業のときの成績はビリのほうだった。彼はモスクワのある役所の所長に就いていたが、その職は妹のアンナの夫であるカレーニン氏の世話で得たもので、カレーニン氏がその役所を統括する省の要職に就いていたのだった。モスクワとペテルブルグの人士の半数がオブロンスキーの縁者もしくは友人で、彼の生まれた階層は、この世の有力者もしくは有力者に成りあがった人々の階層だった。所長になって3年目になるオブロンスキーは、同僚、部下、上司、関りのある全ての人々から愛され、尊敬されていた。そんなオブロンスキーを役所に訪ねてきた者があった。若い頃からの友人で仲間のリョーヴィンだった。「シチェルバツキー家の人たちはどうしてる? 変わりないか?」と彼は訊いてきた。リョーヴィンが妻の妹のキティに恋していることを知っていたオブロンスキーは、うっすらと笑みを浮かべ、「もしきみがシチェルバツキー家の人たちに会いたいのなら、おそらく今日あの人たちは四時から五時まで動物園に行っているよ。キティがあそこでスケートをするんだ。きみもあそこへ行ってくれたまえ。ぼくも後で寄るから、一緒にどこかで晩飯を食おうじゃないか」と言った。
6章
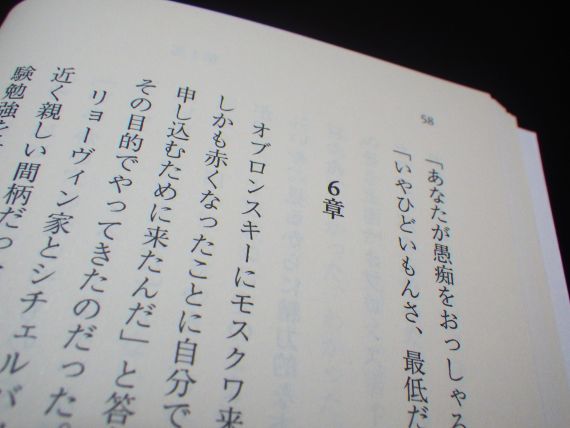
オブロンスキーにモスクワ来訪の目的を訊かれたとき、リョーヴィンが赤くなったのは、「きみの義妹さんに結婚を申し込むために来たんだ」と答えることができなかったからである。実は、彼は、ただその目的でやってきたのだった。リョーヴィン家とシチェルバツキー家は共に古い貴族の家柄で、常に親しい間柄だったので、特に学生時代は、ドリーやキティの兄であるシチェルバツキー侯爵とずっと一緒いて、シチェルバツキー家の三人の令嬢(ドリー、ナタリー、キティ)とも親交があった。学生時代のリョーヴィンは長女のドリーに恋をしかけていたが、彼女はオブロンスキーに嫁いでしまった。次に彼は次女のナタリーを愛しはじめたが、彼女も外交官のリヴォフに嫁いでしまった。リョーヴィンが大学を出る時には、キティはまだほんの子供だったし、海軍に入ったシチェルバツキー若侯爵がバルト海で不慮の死を遂げてしまったので、シチェルバツキー家とは間遠になってしまっていた。だが、今年の冬のはじめ、シチェルバツキー家の人々に出会ったとき、彼は自分が本来三姉妹の誰に恋するべき運命だったのかを悟ったのである。しかし、彼は、醜男で、自分は地上的で下劣な人間であると卑下していたので、一旦は諦めた。それでも、「彼女が妻になってくれるか否かという問題を解決しないうちは、自分は生きていくことができない」と思い直し、彼は、今、モスクワへやってきたのだった。
7章
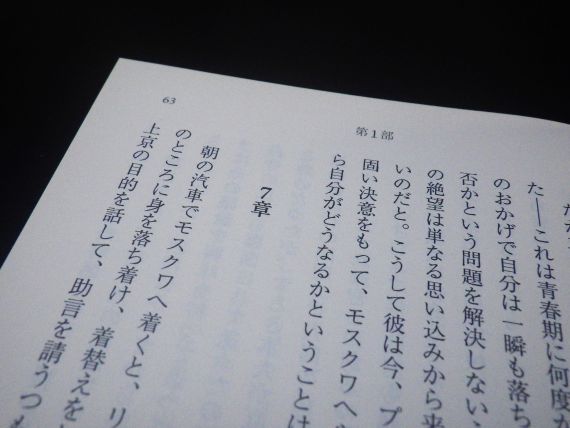
朝の汽車でモスクワに着くと、リョーヴィンは異父兄のセルゲイ・コズヌィシェフのところに身を落ち着け、着替えをしてから兄の書斎に入っていった。すぐに自分の上京の目的を話して、助言を請うつもりだったのである。だが兄は一人でではなかった。ハリコフから来た有名な哲学教授が彼の部屋に坐り込んでいたのだ。この人物は極めて重大な哲学上の問題について、兄との間に生じた誤解を解くためにやってきたのだった。議論のテーマは、人間の活動における心理的現象と生理的現象の間に境界はあるか、あるとすればどこにあるか、というものであった。リョーヴィンは教授が立ち去るまでと思って腰を下ろして待つことにしたが、やがて話に引き込まれていった。兄と教授の会話を聞いているうちに、彼は二人が科学の問題を心の中の問題と結びつけ、何度かほとんどそうした心の問題に迫りかけているのに気づいた。しかしいつでも、いちばん大事な問題の間際まで来ると、二人ともすぐさま急いでそこから後ずさりしているように思った。そこで思い切って質問してみると、教授から怪訝な顔をされてしまったので、リョーヴィンは聞くのをやめて、教授が立ち去るのを待つことにした。
8章
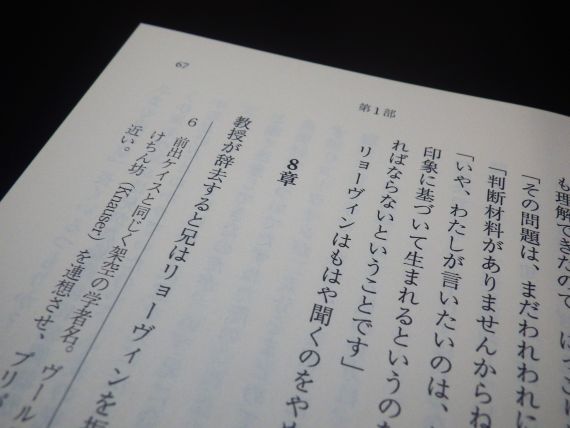
教授が辞去すると、兄はリョーヴィンを振り返り、「ゼムストヴォ(クリミア戦争敗北後のロシア社会の近代化をめざしたアレクサンドル2世が、農奴解放令に加えて、1864年に設置した地方自治機関)はどんな調子だい?」と訊いてきた。コズヌィシェフはゼムストヴォに強い関心を抱き、大変重視していたのだ。リョーヴィンが「もうメンバーじゃない。ぼくはやめたんだ」と答えると、とても残念がった。兄が「ところで知ってるか、ニコライのやつがまた出てきているぞ」と言った。ニコライはリョーヴィンの実の兄で、破滅した人間であり、財産の大部分を蕩尽し、風変わりな仲間と付き合っていて、兄弟と仲たがいしていた。コズヌィシェフがニコライの住居を突き止め、トゥルビンに切った手形を立て替えておいたやつを届けてやると、「頼むからぼくのことは放っておいてほしい」との返事が来たという。「ぼくはニコライ兄さんのところに行ってみるよ」とリョーヴィンが言うと、「行きたければ行ってくるがいい。ただしおれは勧めないけれどね」とコズヌィシェフは言った。リョーヴィンはすぐさま兄のところへ出かけよとしたが、しばし考えた末に出かけるのは晩まで延期することにして、キティに会えると言われた場所へ出かけていった。
9章
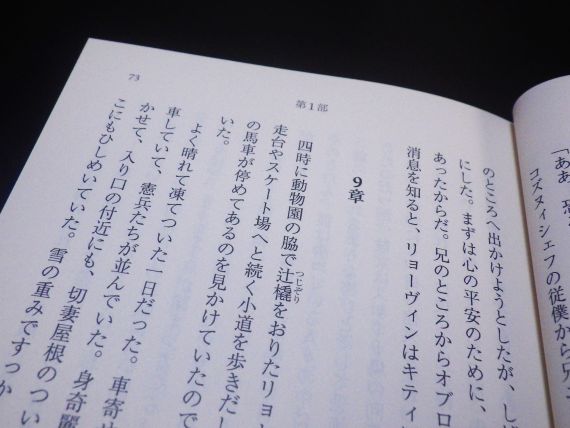
4時に動物園の脇で辻橇をおりたリョーヴィンは、高鳴る胸を意識しながら、橇の滑走台やスケート場へと続く小道を歩きだした。滑走台のところに差し掛かると、彼は、滑っている人々の中に彼女(キティ)の姿を見分けた。スケートを履いた姿でベンチに掛けていたキティの従兄のニコライ・シチェルバツキーが、「おや、ロシアで一番のスケート名人だ!」とリョーヴィンに声をかけてきたが、彼の目はキティを一瞬たりとも視野から外すことはなかった。キティがまっすぐシチェルバツキーのところまで滑ってきて、にっこり笑ってリョーヴィンにお辞儀をした。彼が想像していたよりもずっときれいだった。「ぜひあなたの滑るところを拝見したいわ。スケートをつけて、一緒に滑りましょうよ」とキティが言ったので、リョーヴィンは、「すぐに履いてきます」と言って、貸しスケート屋に出かけ、スケート靴を履いて氷の上に飛び出した。キティが手を差し出して、二人は並んで滑りだし、徐々に速度を上げていった。加速するにしたがって、彼女は彼の手を強く握りしめた。「今度は長く御滞在ですか?」とキティがたずねると、「わかりません」とリョーヴィンは答えた。「どうしておわかりにならないの?」。「わかりません。あなた次第だからです」。言った途端、彼は自分の言葉に愕然とした。彼の言葉が聞こえたのか、それとも聞こえないふりをしたのか、キティは急いで彼から離れていった。キティは思っていた。「でもいったいわたしが悪いのかしら、何か悪いことをしたかしら? みんな思わせぶりが良くないって言うけれど。自分があの人を愛しているのではないことは、自分でもわかっている。でもやっぱりあの人といると楽しいし、あんなにすてきな人なんだもの。ただ、なぜあの人はあんなことを言ったのかしら?……」と。立ち去ろうとしているキティと母親に追いついたリョーヴィンに、侯爵夫人は、「いつもどおり、宅では木曜日にお客さまをお迎えしておりますから、いらしていただければ大変に嬉しゅうございます」と言った。キティもにっこりと微笑んで言った。「またお会いできますわね」。そのとき、オブロンスキーが園内に入ってきて、リョーヴィンの手をつかみ、「さてと、出かけるかい?」と言った。「出かけよう、出かけよう」幸せなリョーヴィンは答えた。彼に耳にいまだ「またお会いできますわね」という「声」だけが響き、目にはそれを言った人の微笑が見えているのだった。
10章

オブロンスキーと一緒にホテルに入っていくとき、リョーヴィンは連れの顔にも全身にも、秘めた輝きとでもいうべき一種独特な表情が浮かんでいるのに気づかずにはいられなかった。オブロンスキーはコートを脱ぐと帽子を横っちょにかぶったままレストランへ向かったが、その間も燕尾服姿でナプキンを持ってくっついてくるタタール人のウエイターたちにあれこれと指示を出していた。ホテルでは、牡蠣、春野菜のスープ、ヒラメの濃いソースかけ、ローストビーフ、去勢鶏、野菜の蒸し煮などを注文し、食した。「ところで、今晩はうちの実家へ、つまりシチェルバツキー家へ客に行くのかい?」と、オブロンスキーが訊くと、「うん、必ず行くよ」と、リョーヴィンは答えた。オブロンスキーが「ロシアにはいったい何をしに来たんだい?」と訊くので、「想像はつくだろう?」とリョーヴィンは答え、「これが成り立つ話だと思うか?」と訊き返した。「若い女はみんな、求婚されれば誇らしく思うものだ」とオブロンスキーが答えると、リョーヴィンは、「若い女性はみんなそうかもしれないが、あの人は別だよ」と言った。リョーヴィンにとって世界には二種類の女性しかいなかった。一種類は彼女を除いた世のすべての女性で、あらゆる人間的欠点をもった、ありふれた女性たち、そしてもう一種類は一人彼女のみであり、完全無欠、あらゆる人間的なものを超越した存在なのだ。「恐ろしいのは、ぼくらみたいに年をくっていて過去のある者が……それも愛の過去じゃなくて、罪の過去を持つ者が……急に純粋な、穢れなき存在とくっつくということだ。これは汚らわしいことで、どうしても気が引けるよ」とリョーヴィンが言うと、「なに、きみの罪なんてたいしてことはないだろう」とオブロンスキーは言った。
11章
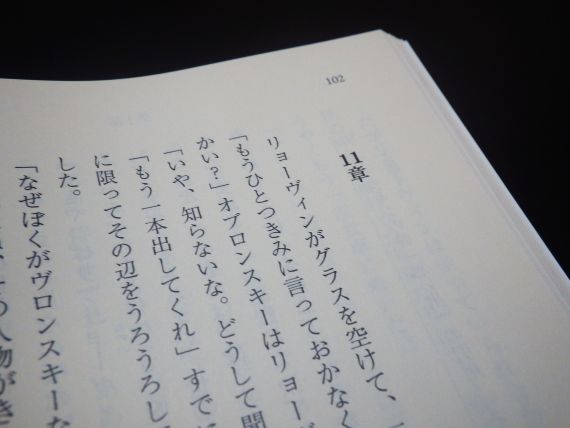
「きみはヴロンスキーを知っているかい?」オブロンスキーはリョーヴィンにたずねた。「いや、知らないな。どうして聞くんだい?」と言ったリョーヴィンに、オブロンスキーは言った。「それはね、その人物がきみの競争相手の一人だからだよ」。ヴロンスキーというのは、キリール・イワーノヴィチ・ヴロンスキー伯爵の息子の一人で、ものすごい金持ちで美男子で縁故も多く、身分は侍従武官、おまけに教養もあって、とても賢く、出世する人物らしい。このヴロンスキーがキティに夢中になっているという。「悪いが、ぼくには何のことかさっぱりわからない」とリョーヴィンが言うと、オブロンスキーは、「ぼくは知っていることをきみに伝えただけだ。もう一度言おう。問題はなかなか微妙でデリケートだけれど、ぼくの読みの及ぶ限りで言えば、きみのほうに勝ち目があるよ。なるべく早く話をまとめるように忠告しておくよ」と言った。さらに、「今日はこの話はしないほうがいいが、明日朝から訪問して、古典的にね、結婚の申し込みをするんだ。そうすればきっと神のご加護があるさ……」と付け加えた。オブロンスキーは、リョーヴィンに、自分の浮気と妻のことを相談するが、「悪いが、ぼくにはまったく理解できない。今のぼくみたいにたらふく食ったばかりの人間がたまたまパン屋の前を通って、通りがかりにひょいとロールパンを一個盗むなんてのは理解できないだろう。それと同じさ」とリョーヴィンは答えた。「なぜだい? ロールパンてのは、時にはつい手が出るほどいい匂いをさせてるじゃないか」とオブロンスキーは言った後、「一体どうすればいい?」とさらに訊くと、リョーヴィンは、「パンを盗まんことさ」と答えたのだった。
12章
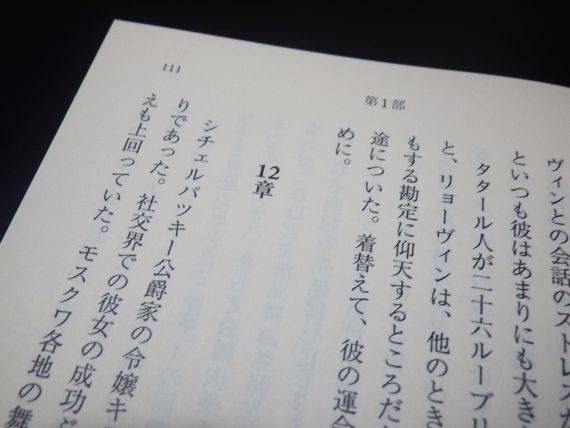
シチェルバツキー公爵家の令嬢キティは18歳、この冬社交界にデビューしたばかりであった。社交界での彼女の成功ぶりは二人の姉以上で、母親の公爵夫人の期待さえも上回っていた。モスクワ各地の舞踏会で踊る若者たちがほとんど全員キティに夢中になってしまったばかりか、初めての冬だというのにもう立派な婿候補が二人も現れた。リョーヴィンと、彼が去った後すぐに現れたヴロンスキー伯爵である。父公爵はリョーヴィンの肩をもち、公爵夫人はリョーヴィンのことが気に入らず、娘にはもっといい結婚相手が現れると期待を持っていた。なので、ヴロンスキーが現れたときには、彼女は喜んだ。ヴロンスキーは大変な金持ちで、賢くて、名門で、侍従武官としての輝かしいキャリアの途上にあり、しかもきわめて魅力的な人物で、母親の願いをすべて満たしていた。ヴロンスキーとリョーヴィンではまったく比べ物にならなかった。目下の彼女の心配は、ヴロンスキーがただ娘をちやほやするだけですませてしまうのではないかということであった。娘がすでに彼を愛しているのを知っていたので、相手は誠実な人間だから、まさかそんな期待はずれなことはするまいと思って自分を慰めていたのである。家に戻ったとき、公爵夫人はキティに訊ねた。「いったいあの方(リョーヴィン)、もう前から戻っていらしたの?」「今日いらしたのよ、お母さま」「ひとつ言っておきたいことがあるわ」公爵夫人は切り出したが、キティは、「お願いだからそのことは何もおっしゃらないで。わたしわかってます、全部わかってますから」と言った。
ここまで、アンナ・カレーニナは(まだ)登場しない。(笑)
『アンナ・カレーニナ』は、
アンナの恋愛と、リョーヴィンの結婚という、
二つのメイン・プロットの周りに、
多様性を持った複数のテーマ群が自在に展開されるという、
幅と厚みのある構成になっている……ということは、
以前に一度読んでいるので、知ってはいたが、
リョーヴィンと、アンナの不倫相手となるヴロンスキーは登場しているのに、
第1部、12章までアンナは登場しない。
じらされるし、そこが実に巧い。
ここまで読んできて、やはり望月哲男訳はとても読みやすいと思う。
この『アンナ・カレーニナ』は、
1875年(明治8年)から雑誌に連載され、
1877年(明治10年)に単行本初版が刊行されている。
(日本では「西南戦争」の頃である)
40代後半の円熟期の大作ということになる。
今読んでも、本当に面白い。
今回も、『カラマーゾフの兄弟』のときと同じく、
一度読んだ後に、二度、三度と読み返しながら要約し、
ゆっくり尺取虫のように読み進めている。
「とにかく読破すればいい」と思っていた学生時代と違って、
今は、じっくり味わいながら読んでいる。
これが、70代の私に、
素晴らしく充実したひとときを与えてくれている。
感謝。
早くアンナに逢いたい!(コラコラ)
イワン・クラムスコイ作「邦題:忘れえぬ女」(1883年)。
アンナ・カレーニナをイメージしたものとも言われている。

