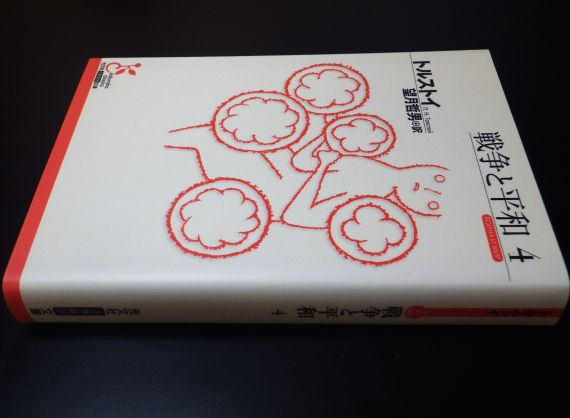
一人読書会『戦争と平和』の9回目は、
第4巻の、
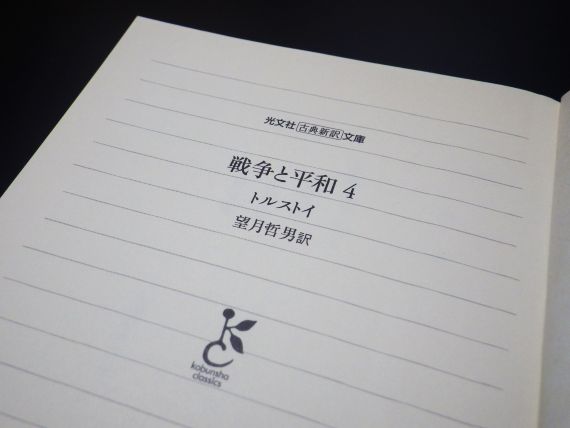
第3部、第1編の1章から23章を読んでみたいと思う。
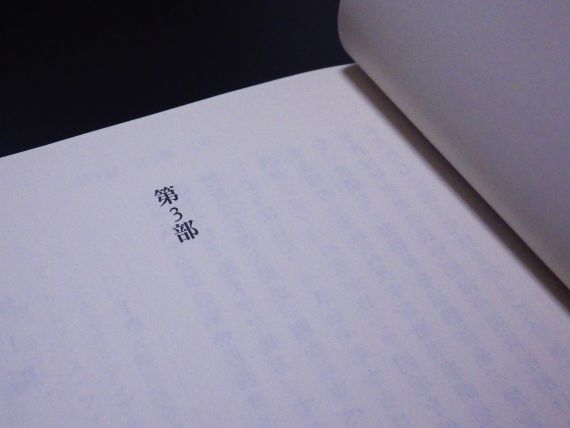
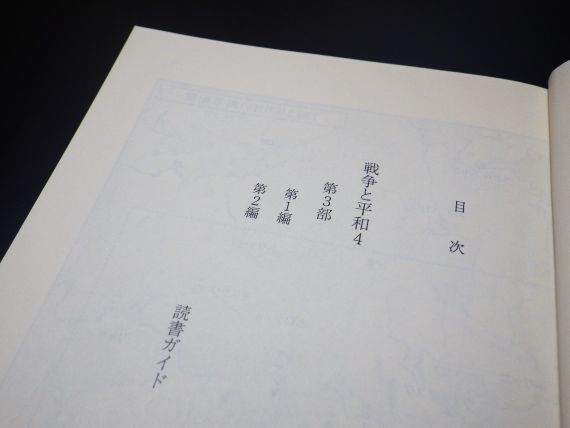
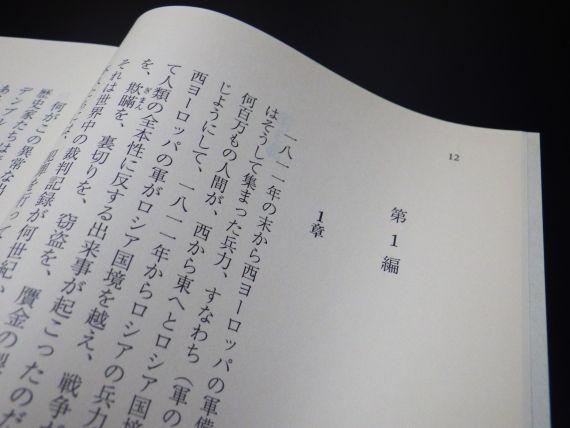
1章
1811年の末から西ヨーロッパの軍備増強と兵力集中が開始され、1812年にはそうして集まった兵力、すなわち何百万もの人間が、西から東へとロシア国境を目指して移動した。そこには同じようにして1811年からロシアの兵力も結集していたのだった。6月12日、西ヨーロッパの軍がロシア国境を越え、戦争が始まった。戦争の原因は無数に考えられるが、どの一つをとっても取り分けて原因とすべきものはなく、出来事はただ起こらざるを得なかったために起こらざるを得なかったということになる。西の人々が殺し合いのために東に進んできた。すると諸原因符合の法則によって、この運動を促し戦争を促す何千もの小さな原因がひとりでに形成され、この出来事に連動したのである。数限りない原因のどれもが原因とは言えない。すべてはあらゆる生命の、有機的な、自然の営みが行なわれるための、諸条件の符合にすぎない。
2章
5月29日、ナポレオンはドレスデンを出た。軍は西から東へ移動し、6月10日には彼は軍に追いついた。翌日ナポレオンは軍を追い越し、幌馬車でネマン川に乗り付け、河岸に出て行った。対岸には聖都モスクワがある。その対岸を見たナポレオンは、皆の予想に反して、進撃を命じた。6月13日、ナポレオンは献上されたアラブ馬でネマン川にかかった橋の一つへと向かった。道中ずっと耳を聾するような歓呼の声に包まれた。ナポレオンは川をひとわたり見渡すと馬を下り、川岸に転がっていた丸太に腰を下ろし、対岸を観察した。そして「浅瀬を見つけて対岸に渡れ」と命令した。ポーランド槍騎兵連隊の隊長が興奮のあまり「浅瀬を探すことなく自分の連隊を率いて泳いで渡河することをお許し願いたい」と申し出て、「万歳」と叫びながら馬に拍車をかけて川に飛び込み、何百人もの槍騎兵が後に続いた。必死に泳いだが、40名ばかりの槍騎兵が川で溺死した。大半の兵士たちは後戻りしてこちら側の岸に打ち寄せられたが、連隊長と何名かの兵は川を渡り切り、「万歳!」と叫んだ。その晩、ナポレオンは、ロシアに持ち込むためのロシア紙幣の偽札を迅速に取り寄せること、一人の(スパイ容疑の)ザクセン人を銃殺すること、必要もないのに川に飛び込んだ例のポーランドの連隊長を名誉部隊の一員に加えるという命令を出した。
3章
一方ロシア皇帝はすでに一月以上もヴィルナに滞在して、閲兵やら演習やらを行っていた。皆が戦争を待ち構えており、皇帝もその準備のためにペテルブルグからやって来たのだったが、その戦争の準備は何一つなされていなかった。ナポレオンがネマン川渡河の命令を発し、彼の前衛軍がコサック兵たちを押しのけてロシア国境を越えたまさにその日(6月13日)、アレクサンドル一世はベニグセンの別荘にいて、侍従将官たちの主催による舞踏会で宵を過ごしていた。ベズーホフ夫人エレーヌもこの舞踏会に参加していて、そのロシア的な美によって、繊細なポーランドの貴婦人たちの輝きを奪っていた。ボリス・ドルベツコイもまた、自称独身者としてこの舞踏会の場にいた。ボリスは、側近の一人である侍従将官のバラシェフが皇帝に歩み寄り話し始めた途端、皇帝の顔に驚愕の表情を浮かべたのを見た。そして、「宣戦布告もなしでロシアに侵入するとは。私は、武装した敵が私の土地から一人もいなくなるまでは和睦しない」という皇帝の言葉を耳にする。皇帝は舞踏会から戻ると、深夜2時に秘書官のシシコーフを呼び寄せ、全軍への命令と元師サルティコフ公爵に宛てた詔書を書くように命じた。翌日、ナポレオン宛てのフランス語書簡が書き上げられた。
4章
6月13日午前2時に、皇帝はバラシェフを呼び寄せると、ナポレオンに宛てた自分の書簡を読み聞かせたうえで、その書簡を届けて、手ずからフランス皇帝に渡すよう命じた。13日から14日にかけての深夜に出発したバラシェフは、明け方にはネマン川のルィコンティ村にあるフランス軍の前哨に着いた。フランス軍騎兵隊下士官が停止を命じた。バラシェフが名乗ると、下士官は将校に伝えるべく兵を遣わした。大佐が出てきて、2キロ先に師団長がおり、彼がバラシェフを迎えてしかるべき場所へ案内するという。一軒の居酒屋を過ぎて丘に差しかかった途端、行手の丘のかげから一群の騎馬の者たちが姿を現した。先頭に立つのは、いまや「ナポリ王」の称号を得た、かのミュラだった。「バル・マシェーブ卿ですな!」王は言った。「どうやら戦(いくさ)が始まりそうな雲行きですな」「陛下」バラシェフが答える。「わがロシア皇帝は戦争を望んではおりません」ミュラは言った。「私が心底願うのは、二人の皇帝がお互いの間で問題を解決してくださって、私の意に反して始まったこの戦争が一刻も早く終わることですよ」ミュラは右手を軽く振って言った。「将軍、これ以上お引止めはしません。お役目のご成功を祈ります」先へ進むバラシェフは、ミュラの言葉から、ごく速やかにナポレオン本人に面会できるものと思い込んでいた。しかし速やかに会えるどころか、次の村の手前でダヴーの歩兵軍団の哨兵が、先刻の歩哨線での時と同様に彼をとどめ、軍団長の副官が呼び出され、彼を村にいるダヴー元師のもとに引率することになったのだった。
5章
ダヴーとはナポレオンにとってのアラクチェーエフであった。アラクチェーエフのような臆病者ではなかったが、やはり同様に謹厳実直で、残忍で、残忍さによってしか自らの忠誠心を表現できない人物であった。バラシェフが訪れた時、ダヴーは農家の納屋の中で樽を椅子にして座り、書類仕事をしていた。ダヴーはバラシェフの顔を一瞥すると、腰を上げようともせず、不機嫌な顔になって、意地悪くほくそ笑んだ。「封書はどこにあるのです?」彼は言った。「私にください、私が皇帝に送っておきます」バラシェフは、自分は皇帝ご自身に直接封書を渡すよう命じられているのと言明した。「貴国の皇帝の命令は貴軍の中では遂行されますが、ここでは、あなたは当方の指示に従わなくてはなりません」とダヴーは言った。「あなたはしかるべき対応を受けるでしょう」そう言うと彼は封書をポケットに入れて、納屋を出て行った。翌日ダヴーは早朝に出立したが、その前にバラシェフを呼び寄せ、指示があったら軍装班とともに移動するように、またムッシュー・ド・カストレ意外誰とも口をきかないようにしていただきたいと告げた。4日間をバラシェフは孤独と無聊と、服従と無力の意識のうちに過ごした。そしてそうしている間にも、フランス兵とともに何度か行軍し、そして最後に今やフランス軍に占領されたヴィルナの町の、4日前に自分がそこから出て行った市門をくぐることになったのだった。翌日、皇帝の侍従ムッシュー・ド・テュレンヌが訪れ、謁見の栄を授けたいという皇帝の意志をバラシェフに伝えた。ナポレオンがバラシェフを迎えたのは、まさにアレクサンドル皇帝が彼を送り出したあのヴィルナの屋敷であった。
6章
ナポレオンはとびきり上機嫌であった。「ようこそ、将軍! お届けいただいたアレクサンドル皇帝の書簡は受け取っています。お目にかかれて欣快です。私は戦争を望んでいませんし、望んだこともありません。しかし私に戦争を余儀なくさせた者がいるのです」友好的な口調から、バラシェフはナポレオンが和平を望んでおり、交渉に入ろうとしているという確信を得た。バラシェフは言った。「アレクサンドル皇帝はクラーキンがパスポートを請求したことが戦争の十分な理由になるとは思っていません。クラーキンは自分の恣意で、皇帝の了解も得ずにああいう行動をとったものであります。アレクサンドル皇帝は戦争を望んでおらず、またイギリスとの間には何の関係もありません」と。「今はまだないということですね」ナポレオンは一言口をはさみ、先を続けるように促した。「アレクサンドル皇帝は和平を望んでいますが、ただし交渉に応じるのは一つ条件があり、それは……」そこでバラシェフは言い淀んだ。「武装した敵が一兵でもロシアの国土に残っているうちは……」という例の言葉を彼は言えなかった。「その条件はフランス軍がネマン川の背後まで退却することです」と言った。ナポレオンの顔色がさっと変わり、左足のふくらはぎがぴくぴくと震えだした。「仮に貴国が私にペテルブルグとモスクワをくれたとしても、私はかような条件はのまないだろう。貴国はイギリスと同盟を結んだ。そして自分の状況が悪くなった今となって、私に交渉を持ち掛けてくるのだ!」ナポレオンは自分の話の制御が利かなくなり、フランス軍の優位性を滔々と喋り続けた。バラシェフに反論の余地を与えなかった。「皇帝陛下への私の書簡は後でお渡ししよう」そう言うとナポレオンは足早にドアへと向かった。
7章
ナポレオンからあれだけのことを聞かされ、最後には素っ気なく「皇帝陛下への私の書簡は後でお渡ししよう」とまで言われたバラシェフは、ナポレオンはもはや自分に会うことは望まないどころか、会うことを避けるだろうと思い込んでいた。しかし驚いたことに、彼は同じ日に皇帝の食卓へ招待を受けたのであった。ヴィルナの町を馬で散歩してきた皇帝は大変な上機嫌だった。町では群集が歓呼の声で彼を迎え、見送ってくれたのだ。ディナーの場でバラシェフを自分の隣に座らせると、ナポレオンは彼に愛想よく接するばかりか、まるでバラシェフもまた自分の廷臣の一人であり、自分の計画に賛同し、自分の成功に歓喜するはずの存在だと思い込んでいるような態度をとった。食事の後で一同はコーヒーを飲むためにナポレオンの執務室に移動した。4日前まではアレクサンドル皇帝の執務室だった部屋である。「この部屋で4日前にアレクサンドル皇帝が私の個人的な敵たちを集めて話し合いをしたが、私にはそれが理解できない。彼は考えてみなかったのだろうか、私にも同じことができるということを?」彼はバラシェフに問いかけた。「彼に知らしめてやろう、私が実際にそうすることを。私はドイツから彼の親戚をすべて追放する。連中の逃げ場は皇帝がロシアに作ればいいのだ」バラシェフの辞去の礼に軽い会釈で応えると、彼は言い添えた。「この方に馬をやりなさい、長道中になるから……」バラシェフが持ち帰った書簡は、ナポレオンからアレクサンドル皇帝に宛てた最後の書簡となった。交わされた会話も詳細にロシア皇帝に伝えられ、そうして戦争が始まった。
8章
モスクワでピエールと会った後、アンドレイ公爵はペテルブルグへ発った。家族には仕事の旅だと言ったが、本当は向こうでアナトール・クラーギン公爵と会うのが目的だった。だがアナトールはもはやペテルブルグにはいなかった。ピエールがこの義兄に、アンドレイ公爵が後を追っていくと耳打ちしたので、直ちに陸軍大臣から任命を取り付け、モルダヴィア駐留のロシア軍に赴任してしまったのである。ちょうどこの時、アンドレイ公爵はペテルブルグでかつての上官・クトゥーゾフ将軍と再会し、「一緒に在モルダヴィア軍に行かないか?」と持ち掛けられ、総司令部付きの命を受け、トルコ国境をめざして出発した。アナトールに書状で決闘を申し込むのは好ましくないとアンドレイ公爵は思っていた。新しいきっかけもなしで自分から決闘を申し込んだりすれば、ナターシャの名誉を穢すことになると思ったからだ。彼はなんとかアナトールと直に出会って、新しい決闘のきっかけを見つけてやろうとしていたのだった。しかしトルコ戦線の軍でも彼はアナトールに会うことはできなかった。アンドレイ公爵が当地に着いて間もなく、相手がロシアに戻ってしまったからである。クトゥーゾフ司令部の当直将官の職に就いた彼は、仕事に専念し、やる気と几帳面さでクトゥーゾフを驚かせた。1812年、対ナポレオン戦争の知らせがブカレストまで届くと、アンドレイ公爵はクトゥーゾフに西部軍への転属を願い出て、バルクライ・ド・トーリのもとに赴く任務を与えられた。そこへ行く前に、アンドレイ公爵は禿山に立ち寄った。父親の老公爵は、娘のマリヤが迷信深く、マドモアゼル・ブリエンヌに冷たいと言って非難した。アンドレイ公爵は、「マリヤは悪くありません。悪いのはあのフランス女(マドモアゼル・ブリエンヌ)ですよ」と妹を庇った。老父は激怒し、息子に「出て行け、出て行くんだ!」と怒鳴り声をあげた。アンドレイ公爵は直ちに立ち去ろうとしたが、マリヤに懇願されてあと一日だけ残ることになった。「あんなくだらない人間のおかげで人々が不幸になるなんて!」そう言う兄に対し、マリヤは、「お兄さま、ひとつだけお願いがあるの。悲しみをもたらすのは人間だと思ってはだめよ。人間は神さまの道具にすぎないのだから。悲しみは神が遣わすもので、人間が遣わすものではないわ。人間は神さまの道具で、人間に罪はない」と言った。
9章
アンドレイ公爵は6月の末に軍の総司令部に到着した。皇帝がいる第一軍は、ドリッサ川のそばの要塞陣地にいた。第二軍はフランス軍の大軍勢によって第一軍から分断され、いったん後退して第一軍との合流を図っていた。アンドレイ公爵はバルクライ・ド・トーリ将軍を、ドリッサ川の岸辺で見つけた。素っ気なく冷淡な態度でアンドレイ公爵を迎えた将軍は、君のことは皇帝に報告したうえで任務を決めるから、それまでは自分の司令部に所属するようにと言った。軍で見つかると期待していたアナトールはここにもいなかった。ペテルブルグに戻っていたのだ。まだどこにも用務のない最初の4日間、アンドレイ公爵は要塞陣地の全体を馬で回り、自分の知識と情報通の者たちとの会話をたよりに、この陣地に関するきちんとした理解を頭の中に形成すべく努めた。そして彼なりに次のように理解した。皇帝は総司令官の肩書を持ってはいないが、全軍を支配下に置いており、皇帝を取り囲む人々は、彼の補佐である。この巨大な、騒然とした、きらびやかな、誇り高い世界で交わされるあらゆる思想や意見の中に、アンドレイ公爵は9つの派閥の区分を見て取った。➀プフールと彼の追随者のような戦争理論家の派閥。➁第一の派閥の正反対の派閥。③一番皇帝の信頼が厚い派閥。④皇帝後継者である大公を一番目立つ代表とする派閥。⑤バルクライ・ド・トーリの信奉者の派閥。⑥ベニグセン派の派閥。⑦皇帝の、とりわけ若い皇帝の周囲に常にいるような取り巻きたちの派閥。⑧(最大派閥で)自分にとって最大の利益と満足を求めている派閥。⑨高齢の、賢明な、国政の経験に長けた者たちの派閥。第九の派閥のメンバーたちは、〈諸悪の根源は主として皇帝が侍従武官を引き連れて軍に身を置いていることである。それ故に曖昧で形式的でどっちつかずの不安定な雰囲気が軍に持ち込まれてしまったが、それは宮廷には向いていても軍には有害なものである。皇帝がなすべきことは統治することであって軍を指揮することではない。この状況を打破する唯一の方法は、皇帝が侍従武官を引き連れて軍を去ることである〉と考え、この派の主要メンバーの一人であったシシコーフが皇帝に書状を認(したた)めた。そして皇帝はそれを軍を去る口実として受け入れたのでる。
10章
この書状がまだ皇帝の手に渡っていない時、バルクライが食事の席でアンドレイ公爵に、皇帝は直々にアンドレイ公爵と会見し、トルコのことで質問したいとのご意向なので、翌日の午後6時にベニグセンの宿舎に出頭するようにと告げた。この日の朝、ミショー大佐が皇帝のお供でドリッサの堡塁を視察して回りながら、プフールが築いた要塞陣地が、実は何の役にも立たぬ代物で、ロシアの破滅の種になるだろうという説明をしていた。皇帝の意向で会議が招集され、皇帝が目前の難局に関する意見を聞きたいと思う者たちが集められていた。プフールはアンドレイ公爵のすぐ後からやって来た。プフールは背は低くひどく痩せており、理論派のドイツ人一般が持つ諸特徴を一身に集めた人物だった。1806年にプフールは戦争の作戦立案に加わったが、自分の理論が間違っているという根拠は何一つ見出さなかった。プフールは、自分の理論を愛するあまり、理論の目的とすること、すなわち実践への応用を忘れてしまうタイプの理論家だった。プフールが次の間に入って行くと、すぐにそこから低音で愚痴っぽく喋る彼の声が聞こえてきた。
11章
アンドレイ公爵がプフールの去っていく姿を見届ける暇もなく、部屋の中に急ぎ足のベニグセン伯爵が入ってきて、立ち止まりもしないで自分の副官に何か指示を与え、奥の部屋に向かった。皇帝は馬でこちらに向かっているところで、ベニグセンは皇帝を迎える準備をするために一足先に着いたのだった。チェルヌィショフとアンドレイ公爵は表階段に出て行った。皇帝はアンドレイ公爵に優しく声をかけてきた。「よく来てくれた。皆が集まっている部屋に通って、そこで待っていてくれたまえ」そう言うと皇帝は書斎に入っていった。アンドレイ公爵は、会議が行われる客間に入っていった。ヴォルコンスキー公爵が書斎から出てくると、地図をテーブルの上に広げ、諸君の意見をうかがいたいと告げた。アルムフェルト将軍が口火を切り、まったく新しい布陣を提案してみせた。若いトーリ大佐が将軍の意見を激しく論駁し、アルムフェルトの案ともプフールの案とも完全に対立する作戦計画を提起した。ヴォルコンスキー公爵がプフールに意見を求めると、「私などに何をお訊ねになるのですか? だって皆さんご自身、私などよりすべてを良くご存知じゃないですか」と言った。ヴォルコンスキー公爵が、自分は皇帝の名代としてあなたの意見を聞いているのだと言うと、プフールは「何もかもぶち壊し、何もかもめちゃくちゃにして、今になってどうやって立て直せばいいのかと訊くわけですか? なにも立て直すことなんかありませんよ。何もかも私が述べた原理の通り、きちんと実行すれば済むことです」と言った。アンドレイ公爵の共感を呼んだのはプフールだけだったが、彼の凋落は間近で、それを皆も知り本人も感じていた。翌日の接見の折、皇帝はアンドレイ公爵にどの部署での勤務を希望するかと訊ねた。アンドレイ公爵は(皇帝の側近としての勤務を願い出るのではなく)軍に勤めることをお許し願いたいと答え、宮廷世界との縁をみずからすっぱりと切ることになったのだった。
12章
開戦の直前にニコライ・ロストフは両親からの手紙を受け取ったが、そこにはナターシャが病気になったこととアンドレイ公爵との婚約が破断になったことが手短に告げられ、親たちはまたもや彼に退役して帰郷するように求めていた。ニコライは退役も休暇も願い出ようとはせずに、ただ両親に宛てて「自分もあなた方の願いを実現すべくできる限り努力をする」と書き送った。休暇中に彼は騎兵大尉に昇進しており、また元の騎兵中隊を任されることとなった。軍はヴィルナから退却しつつあった。スヴェンツィヤーヌィからさらに次々と撤退が続いてドリッサに至り、ドリッサからもまた撤退して、もはやロシア国境に近づいていた。7月13日、パヴログラード連隊は初めて本格的な戦闘に入ることになった。戦闘前日の7月12日の深夜は、激しい雷雨だった。ニコライと若い将校のイリインと二人で掘っ立て小屋にいたが、そこへ彼らの連隊の将校ズドルジンスキーが飛び込んで来て、伯爵、ラエフスキー将軍の快挙をお聞き及びですか?」と言った。その快挙とは、ラエフスキーが激烈な砲火の下、自分の息子二人を堤防に上らせ、親子そろって攻撃をかけたことを指していた。ニコライはズドルジンスキーの賛辞にさっぱり同感の意を示さなかったばかりか、逆に聞かされた話を恥ずかしく感じていた。ズドルジンスキーの話がニコライの気に入らないのを見て取ったイリインは「靴下もシャツもびしょ濡れです。どこか避難所を探してきます」と言って出て行くと、ズドルジンスキーも立ち去った。5分後、イリインが駆けつけてきて「居酒屋が見つかりました。マリヤ・ゲンリホヴナも来てますよ」と言った。マリヤ・ゲンリホヴナは連隊の軍医の妻である若いきれいなドイツ女性で、軍医がポーランドで結婚した相手だった。ニコライはマントを引っ掛けるとイリインとともに歩き出した。
13章
居酒屋の前に軍医の幌馬車が停まっており、店の中にはすでに5人ばかりの将校が集まっていた。ふくよかな金髪のドイツ人女性マリヤ・ゲンリホヴナはカーディガンを着てナイトキャップをかぶった姿で、入口側の片隅の大きな長椅子に座っていた。夫の軍医は妻の後ろで眠り込んでいる。入って行ったニコライとイリインは陽気な喚声と笑い声で迎えられた。壊れたペチカに火が起こされ、二つの鞍の上に板を乗せて、その上にサモワールやラム酒の瓶を並べ、マリヤ・ゲンリホヴナにホステス役をお願いして、皆がその周りに集まっていた。この晩の将校たちはみんな、マリヤ・ゲンリホヴナに恋をしてしまったようだった。スプーンは一つしかなく、彼女が順番に皆の砂糖をかき混ぜることに決まった。ニコライは自分のコップにラム酒を注ぐと、マリヤ・ゲンリホヴナにかき混ぜてきださいとお願いした。「あら、お砂糖が入ってないじゃありませんか?」彼女が言った。「ええ、僕は砂糖はいりません。あなたの手でかき混ぜていただきたいのです」マリヤ・ゲンリホヴナは承知してスプーンを探したが、それはすでに誰かの手に渡っていた。「指でしていただけませんか、マリヤ・ゲンリホヴナ」ニコライは言った。「その方がうれしいです」サモワールの湯が飲み干されると、ニコライの提案で「キング」ゲームが始まった。見事キングになった者がマリヤ・ゲンリホヴナの手にキスをする権利を獲得するというのがゲームのルールだった。しかしゲームが始まった途端、夫の軍医が目を覚まし、軍医は妻を連れて幌馬車に戻ってしまった。将校たちは居酒屋の中で濡れた外套にくるまって横になったが、長いこと寝付けぬままだった。
14章
2時を過ぎてもまだ誰も眠りについていなかったが、そこへ曹長が現れてオストロヴナ村方面へ出動せよという命令を伝えた。ニコライは中隊めがけて歩き出した。すでに夜が白みかけていて、雨は止み、雲も散ろうとしていた。居酒屋を出たところでニコライとイリインは軍医の幌馬車を覗き込んだ。ナイトキャップを被った奥方の頭が見えて、寝息が聞こえた。「まったく、実にかわいらしい人だな!」ニコライが言った。「実に魅力的な方です!」イリインが答えた。半時間後には中隊が街道に整列し、「乗馬!」の号令がかかると兵士たちは馬にまたがった。ニコライが「前進!」と号令すると、前を行く歩兵隊と砲兵隊を追う形で、白樺並木の広い道を進みだした。前方で砲声が響いた。副官が駆けつけてきて速足で街道を前進せよとの命令を伝えた。前方の窪地の向こうには敵の縦隊と砲列が見えた。窪地のただ中では、すでに戦闘に入った味方の散兵線が、にぎやかに敵と撃ち交わす銃声が響いている。「縦列組め、突撃用意!」散兵線からヒュルヒュルという音を立てて弾丸が飛んできた。久しく耳にしていなかったその音を聞くと、ニコライは楽しくなり、気合が入ってきた。栗毛の馬に乗った橙色の軍服の槍騎兵たちの間やその背後に、灰色の馬に乗ったフランスの竜騎兵たちの青い大きな塊が見えた。
15章
ニコライは狩猟家ならではの鋭い目で、味方の槍騎兵を追ってくる青いフランス竜騎兵の群れをいち早く見つけた。ニコライは持ち前の感覚で見て取った̶̶もし今、軽騎兵たちを率いてフランスの竜騎兵隊を急襲すれば、相手は持ちこたえられまい。だがもし急襲するなら、今すぐ行うべきであり、ここを逃したらもはや手遅れだ。すぐ横に立っていた大尉に話しかけた。「あいつら、ひねり潰せるんじゃないか……」「そう行けば快挙だが」大尉は言った。「だが実際は……」大尉の言葉をしまいまで聞かずに、ニコライは馬をひと蹴りして中隊の前に飛び出した。するとまだ彼が号令を発しきらないうちに、彼と思いを同じくしていた中隊の全員が、後を追って駈け出したのだった。ちょうどオオカミのゆく手を遮ろうとするときのような心境で、ニコライは馬を全速にし、列を乱したフランス軍竜騎兵たちの行く手を目指して疾駆した。フランス軍竜騎兵の大半は逃げ帰ろうと馬を飛ばしている。ニコライはそのうちの葦毛馬に乗った一人に目を付け、後を追った。ニコライの馬が胸板を相手の将校の馬の尻にぶつけてあわや倒しそうになった。するとその瞬間、ニコライは自分でもなぜか分からず、サーベルを振りかざしてフランス人将校めがけて打ち下ろしたのだった。その瞬間、ニコライの昂った気持ちがすっと消えた。相手の将校は落馬したが、サーベルは手首の上あたりをちょっと切り裂いただけだったので、落馬は馬がぶつかった衝撃と恐怖のためだった。フランス人将校は、金髪のうら若い、顎にくぼみのある、明るい青い目をした、およそ戦場には似合わない青年だった。将校は「降伏する!」と叫んだ。あちこちで軽騎兵たちが捕虜となった竜騎兵の処置に追われていた。前方からフランスの歩兵隊が射撃しつつ駆けつけてくる。軽騎兵たちは急いで捕虜を連れ、早駆けで自陣を目指した。オステルマン=トルストイ伯爵が戻ってきた軽騎兵たちを出迎えると、ニコライを呼び寄せて感謝の言葉を述べ、彼の勇敢な行動を陛下に上奏し、聖ゲオルギー十字勲章の授与を願い出るつもりだと述べた。ニコライには嬉しい驚きであった筈なのに、精神的な吐き気が去らなかった。ニコライはどうしても納得のいかないことがあったのだ。〈つまり敵も俺たち以上に恐怖心を持っているってことだ!〉彼は思った。〈つまり世にいう英雄的な行為とは、たかがこれっぽちのことだったのか?〉しかしニコライがこんなことに悩んでいた間、職務の運勢ががらりと好転した。オストロヴナの戦いの後、彼は抜擢されて軽騎兵大隊を預けられ、勇敢な将校が必要な時には彼に声がかかるようになったのである。
16章
ナターシャが病気だという知らせを受けたロストフ伯爵夫人は、自分もまだ病が癒え切らずに衰弱した身だったにもかかわらず、家じゅうの者を引き連れてモスクワへやってきた。そしてロストフ一家はアフローシモフ夫人のところから自分たちの屋敷へと移り、すっかりモスクワに住みつくことになったのである。ナターシャの病気は極めて重篤だったので、病気の原因になった出来事や婚約破棄のことなどはすべて二の次になってしまった。なにで彼女は食べることも眠ることもせず、みるみる痩せて咳もし始め、危険な状態にあったのだ。医者たちは個別に往診するほかに、揃ってやって来てカンファレンスを開き、自分たちが知る限りの病名をあげて、ありとあらゆる薬を処方した。ナターシャの薬の小瓶やら小箱やらは大変な量にのぼったが、それほどの大量の丸薬や水薬や粉薬を服用したにもかかわらず、結局は若さが勝利した。ナターシャの悲しみは日々の生活の印象の積み重なりに次第に埋もれていって、前ほどの苦しい痛みとなって胸にのしかかることもなくなり、次第に過去のこととなっていった。そうしてナターシャは身体的にも回復し始めたのである。
17章
ナターシャは落ち着いてはきたが、快活になったわけではなかった。舞踏会や馬車でのドライブやコンサートや芝居といった(楽しみをもたらす)外部の刺激を一切避けていたばかりか、すっきりとした笑顔は一度も見せなかったし、歌うこともできなかった。何かをしようとすると、すぐさま涙が胸を塞いでしまうのだ。それは後悔の涙であり、二度と戻らぬ純な時代の追憶の涙であり、いくらでも幸せであり得たはずの自分の青春を滅ぼしてしまったことへの憤懣の涙であった。外出することもほとんどなく、一家を訪れる客の中ではピエールだけを喜んで迎えた。ピエールの彼女に対する態度は、優しく、慎重な、そして同時に真摯なものだった。聖ペテロの精進週の終わりに、ロストフ家のオトラードノエ村の近隣に住む女地主のベローフ夫人アグラフェーナ・イワーノヴナが、モスクワの聖者たちへのお参りにやってきた。夫人がナターシャに精進を勧めたところ、ナターシャは喜んでその考えに飛びついた。夫人は午前3時にナターシャを迎えに来た。慣れない早朝の時間に、勤行の声を追い、その意味を理解しようと努めているうちに、ナターシャはこれまで味わったことのない何か大きな、不可知なものに対する恭順の感覚を覚えるのだった。こうしてまるまる一週間も過ごしているうちに、己の様々な欠点を矯正し、新しい清らかな生活と、そして幸せを得ることができるのだという、新鮮な感覚を味わった。来るべき「領聖」(プリオプシチーツァ)̶̶ベローフ夫人の楽しい語呂合わせによれば「神との交わり」(ソーオプシチーツァ)̶̶の歓びは、ナターシャにはあまりにも望外のものと思えたが、その幸せな日はついに到来した。その記念すべき日曜日に教会から戻った彼女は、この何か月もの間で初めて、自分の心が落ち着いていて、この先の人生を苦にしていないのを感じたのだった。
18章
7月初めになると、モスクワには戦況に関する穏やかならざる噂がどんどん広がっていった。皇帝陛下が国民に檄を飛ばされるとか、陛下御自身が軍を離れてモスクワにおいでになるとかいう話だった。7月11日の土曜日、詔勅が届いたが、まだ印刷されていなかったため、たまたまロストフ家を訪れていたピエールは、翌日の日曜日に昼食に伺うときに、詔勅と檄文をラストプチン伯爵からもらって持参しましょうと約束した。その日曜日、ロストフ一家はラズモフスキー家の教会の祈禱式に出かけた。7月の暑い盛りだった。母と並んで歩いていると、ナターシャの耳に若い男性の声が聞こえてきた。「あれがロストフ家の令嬢だよ、例のね……」彼女の噂をしているのだった。ナターシャは、胸の痛みや恥じらいが募れば募るほどますます落ち着きはらった、堂々とした足取りになるという、女性にこそできる技で前へと進んで行った。端正で静かな老人の司祭が慎み深くも厳かな態度で勤行をしている姿は、祈る者たちの心に荘厳なる慰安というべき効果をもたらした。ナターシャの胸は本人も説明のつかない涙をたたえ、うれしいような苦しいような気持ちが彼女の心を昂らせていた。そこへ司祭が藤色のビロード製の帽子を被って登場し、跪いた。たった今宗務院から届いたばかりの、ロシアを敵の来襲から救うための祈禱が行なわれようとしていたのだ。「万物の主なる神よ、われらの救いの神よ」司祭が静かな声で祈りを始めた。心が開かれた状態にあっただけに、ナターシャにはこの祈りが強烈な作用をおよぼした。正しき心を願い、信仰による、希望による心の強化を願い、われらを愛によって奮い立たせよという祈りに彼女は心から共感した。彼女は胸の内で、人々が犯した罪によって受ける罰に対して、とりわけ自らが罪によって受ける罰に対して、敬虔なる気持ちでおののくような恐怖を覚えていた。だからすべての人々を、そして自分を許し、すべての人々に、そして自分に、人生の平安と幸福を授けたまえと、神に願ったのだった。そして彼女には、神が自分の祈りを聞いてくれているような気がしたのである。
19章
ピエールがロストフ家からの帰途に、ナターシャの感謝のまなざしを思い起こしながら天空に浮かぶ彗星を見つめて、何か新しいものが自分に開示されたと感じたあの日を境に、それまでずっと彼を苦しめていた地上の事柄すべての虚しさや無意味さに関する問題は、ぱったりと頭に浮かばなくなった。頭に浮かぶのは、ただ彼女の面影なのだった。しかし最近になって戦場から頻々と不穏な噂が届くようになり、そしてナターシャの健康が回復し始めて、彼は次第に底知れぬ不安に駆られ始めた。今の自分の状況がこのまま長く続くはずはない。そんな折、ピエールはフリーメイソンの同志の一人からヨハネの黙示録から読み取ったというナポレオンに関する予言を教えられた。黙示録第13章第18節にはこう書かれている。「知恵はここにあり、心ある者は獣の数字を教へよ。獣の数字は人の数字にして666なり」ヘブライ語の数秘術で《皇帝ナポレオン》という綴りのアルファベットを全部数字に直すと、数字の合計が666となり、ナポレオンは黙示録で予言された獣であるということになる。ピエールは自分の名前をこれに適用してみた。すると《ロシア人ベズーホフ》でぴったり666となり、求めている答えを得た。この発見に彼の胸は沸き立った。日曜日の朝ラストプチン伯爵の家に立ち寄ってみると、そこには軍から到着したばかりの急使がいた。かばんの中に手紙がたくさんあり、その中に、ニコライが父親に宛てたものも混じっていたので、ピエールはそれを代理で受け取った。さらに彼はラストプチン伯爵から、印刷したばかりの皇帝のモスクワ市民への檄文と最新の軍関係の通達、それに伯爵自身の手による最新のビラをもらった。中の一通の受勲者の記事の中にニコライの名が挙げられ、聖ゲオルギー第4等勲章受章とあるのを発見した。さらにアンドレイ公爵を狙撃兵連隊長に任ずるとの記事もあった。
20章
日曜日にはいつもそうだが、ロストフ家の午餐には親しい知人の誰彼が集まることになっていた。ピエールはまず家の者たちだけに会いたかったので、早めに馬車で乗り付けた。ロストフ家で彼が最初に見かけたのはナターシャだった。彼女は広間で歌っていたのだった。その声は彼を驚かせ、そして喜ばせた。「伯爵、どう思われます、私が歌うのはいけないでしょうか?」ピエールを見つめながらナターシャが言った。「いや、どうしてですか? いけないどころか……でも、なぜあなたは僕の意見など訊くんです?」「自分でも分かりません。でも私、あなたのお気に召さないようなことは何もしたくないんです」彼女はピエールがこの言葉に顔を赤らめたことにも気づかなかった。「私、あの通達の中にあの方の、ボルコンスキーさんの名前を見ましたわ。あの方はいつか私のことを許してくださるでしょうか? どう思われますか?」「僕が思うに……」ピエールは言った。「あの人が許すべきことなど何もありません……もしも僕があの人の立場だったら……」あの時と同じ憐れみとやさしさと愛の感情が彼を捕らえ、同じ言葉が喉元まで浮かんできた。だが彼女はそれを口にする暇を与えなかった。「ええ、あなたは別ですわ。もしもあなたがいらしてくださらなかったら、あの時もそして今でも、私自分がどうなっていたか分かりません。なぜって……」彼女の目に突然涙が浮かんだ。その時客間から末息子のペーチャが駆け出して来た。ペーチャは今では15歳の紅顔の美少年になっていて、姉のナターシャに似ていた。彼は自分が軽騎兵隊に入れてもらえるかどうか調べてほしいと、かねてからピエールに依頼していたのである。「やあ、どうですか、詔勅は手に入りましたか?」老伯爵は訊ねた。ピエールは直ちに檄文を読み上げようとしたが、「いや、食事の後に取っておきましょう」と老伯爵が言ったので、食事の後に朗読の名手ソーニャが読むことになった。ロシアを脅かす数々の危機と、皇帝がモスクワに、そしてとりわけ名だたる貴族階級に寄せる期待についてのくだりを読んだ後に、ソーニャは声を震わせながら、最後の言葉を読み上げた。「……願わくは、敵がわれらに及ぼさんと企んでいる破滅の運命が敵の頭上に下り、隷属状態から解放されたヨーロッパがロシアの名を褒め称えんことを!」「そのとおりだとも!」伯爵が叫んだ。「陛下のお言葉があれば、われわれはすべてを犠牲にして何一つ惜しみはせん」ナターシャが席を立って父親に駆け寄った。「なんて素敵なんでしょう! うちのお父さまは!」そう口走って父親に口づけすると、ナターシャはピエールをちらりと見た。そこには彼女が生気を回復するとともに戻って来たあの無意識の色気が混じっていた。これまで誰も注意を払っていなかったペーチャが父親に歩み寄ると、真っ赤になって言った。「こうなったらお父さん、僕、思い切って言います。お母さんにも、どう思われてもかまいません。僕を軍務に就かせてください。そうせずにはいられないのです」「おやおや」彼は言った。「また一人兵隊さんの誕生か! まあつまらぬ考えは捨てなさい。勉強しなくてはな」「つまらぬ考えではありません、お父さん。祖国が危機に瀕しているのですから」「もういい、たくさんだ、つまらぬことを……」「でもお父さんが自分で言ったんでしょう、すべてを犠牲にしてと」「ペーチャ、黙れと言っているだろう」伯爵は一喝した。「いいか、まだ口の端の乳も乾かぬ小僧っこが軍人になりたいなんて、とんでもない!」伯爵は書類を手にして、部屋を出て行こうとした。「ベズーホフさん、どうです、一服しませんか……」「いや、僕は家に帰ろうかと……」「どうしてお帰りになるの? どうして?……」挑みかかるように彼の目を見つめながらナターシャがピエールを問い詰める。〈なぜなら、僕があなたを愛しているからです!〉彼はそう言いたかったが、口には出さず、顔を真っ赤にして目を伏せてしまった。彼はなんとか軽い笑みを浮かべようとしたが、できなかった。彼は彼女の手に口づけして部屋を出た。ピエールは二度とロストフ家に出入りするまいと心に誓った。
21章
入隊の意図をきっぱりとはねつけられたペーチャは、自分の部屋に帰って一人閉じこもり、さめざめと泣いた。翌日、皇帝が到着した。ロストフ家の使用人たちの何人かも、暇をもらって皇帝をひと目見ようと出かけて行った。この日の朝、ペーチャは身支度に時間をかけ、髪を梳かし、襟の具合も大人ふうに整えた。そして誰にも告げずに、帽子を被って見とがめられぬようにこっそりと裏階段から外へ出た。ペーチャはまっすぐ皇帝のいる場所へ行き、侍従の誰かに自分ロストフ伯爵は若輩ながら祖国に仕えたいと願っており、年の若さは献身の妨げにはならないので、すぐにでも云々と、直に説明しようと決意していた。しかしクレムリンの間近まで来ると、もはや群集にもみくちゃにされぬようにという注意が先に立ち、気持ちが萎えていった。馬車が全部通り過ぎると、群集が門に殺到し、ペーチャもその勢いで広場まで押し出されたが、そこはもう人でいっぱいだった。群集はしばし一箇所に立ち止まっていたかと思うと、その後また前方に突進した。ペーチャも我を忘れて歯を食いしばり、獣のごとく目をむき出して、肘を使い、「万歳!」と叫びつつ突進した。ペーチャは不意にあばら骨のあたりに強烈な打撃を食らい、ぐいぐい押されたため、急に目の前が暗くなって意識を失ってしまった。気がつくと、白髪交じりの青い聖衣をまとったどこかの聖職者、おそらく堂務者が、片腕で彼の脇を支え、群衆から彼の体を守ってくれているところだった。堂務者は青ざめて息も絶え絶えなペーチャを《大砲の王さま》のところまで連れ出してくれた。ペーチャはじきに意識を回復し、災難の代償として、彼は大砲の上の特等席を獲得し、そこから同じ道を戻るはずの皇帝を見る可能性を得たのだった。祝砲が聞こえ、ウスペンスキー聖堂から将校や将軍や侍従たちが駆けだしてきたかと思うと、その後からゆったりとした足取りで別のお歴々が歩み出てきた。そして最後に軍服に綬を帯びた男性が4人、聖堂の扉から姿を現した。ペーチャは荒々しい声で「万歳!」と叫ぶと、明日はさっそく、どんな犠牲を払ってでも軍人になるのだと決めてしまった。自宅に帰ると彼は断固とした強い口調で、もし軍に出してもらえなければ、自分は家出すると宣言した。
22章
2日後の15日の朝、スロボツコイ宮殿の門前に無数の馬車が並んでいた。宮殿の広間はいずれも人でいっぱいだった。第一の広間には貴族たちが、第二の広間には商人たちが集まっていた。ピエールは早朝から、すでに彼には窮屈になった貴族制服を着込んだ不格好な姿で、広間に入っていた。彼は興奮していた。異例の集会が、久しく思い起こさなかったが胸のうちに深く刻まれていた『社会契約論』やフランス革命に関する一連の思考を、彼に呼び覚ましたからである。皇帝の詔勅が朗読されると皆は歓呼の声で応えたが、それがすむと集団はまたばらけて、それぞれの話を始めた。退役海軍軍人の制服をまとった勇まし気な美貌の中年男性が一人、広間の一つで演説し、その周りの人垣ができていた。ピエールもその輪に加わり、耳を澄ました。イリヤ・ロストフ伯爵もまたこの集団に近寄って、話を聞き始めた。退役海軍軍人の発言は極めて大胆なものだった。ピエールは自分も喋りたいという気になっていた。「失礼ながら閣下」彼は語り出した。「私は決して賛成するものではありません。私の意見では̶̶」聴衆の多くは、元老院議員の見下したような薄笑いに気づき、またピエールが奔放に過ぎる発言をしているのを見て取ると、円陣から離れて行った。
23章
その時、将軍の服を着て肩から勲章の綬を掛けた人物が足早に入って来た。ラストプチン伯爵だった。「皇帝陛下がじきにお見えになります」ラストプチン伯爵は言った。「目下の状況下においてはわれわれがあれこれ議論すべき問題はありません。陛下はわれわれ貴族とそして商人階級を招集されました。あちらからは巨万の金が流れてくるでしょう。一方われわれの務めは、義勇兵を出し、自らも骨身を惜しまぬことです」テーブルに着いている重鎮たちだけの間で会議が始まった。そして「モスクワ市民はスモレンスク市民と同様、1000名につき10名の義勇兵を軍装品一式付きで供出する」というモスクワ貴族会の決議を記録するよう、書記官に命令が下った。皇帝が広間に入って来た。いましがた成立したばかりの貴族会の決議を伝えると、「諸君!」皇帝が一瞬声をうわずらせて言った。「私はロシア貴族の熱情を一度たりとも疑ったことはない。だが本日示されたその熱情は、私の期待を上回るものだ。祖国を代表して諸君に感謝する。諸君、ともに行動しよう。時が何よりも貴重であるゆえ……」皇帝が口を閉じると、四方八方から歓呼の声が上がった。皇帝は商人の広間に移っていった。そしてそこに10分ほどとどまった。ピエールは感動の涙を目に浮かべて商人の広間から出てくる皇帝の姿を目撃した。この瞬間のピエールが感じていたのはただ一つ、自分は何も惜しくない、自分にはすべてを犠牲にする覚悟があることを示したいという願望ばかりだった。マモーノフ伯爵が一個連隊を拠出しようとしているのを知ると、ピエールも即座に1000名の義勇兵とその経費を提供する旨を、ラストプチン伯爵に宣言した。ロストフ老伯爵もこの日の出来事を涙なしに妻に語れなかった。そしてペーチャの願いもたちまち受け入れて、自ら息子の入隊申請に出かけたのであった。翌日皇帝はモスクワを去った。一同に会した貴族たちもみな制服を脱ぎ、またもや各家庭やクラブに身を落ち着けて、ため息を漏らしながら領地管理人たちに義勇兵拠出の件を申し渡した。そうして自分たちがしでかしたことに、驚き呆れたのである。(第3部、第1編終わり)
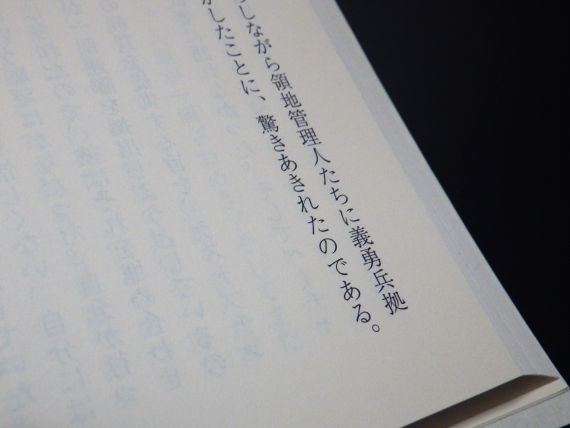
第4巻では、ロシアを舞台とした祖国戦争が描かれる。
1812年5月29日にドリスデンから遠征を開始したナポレオンは、
6月12日には50万の大陸軍を率いてネマン川を渡ってロシアに侵入し、
その後退却を重ねるロシア軍を追って、
ヴィルナ、ヴィテプスク、スモレンスクの諸都市を占領し、モスクワに迫る。
ロシアの一大危機を描くトルストイは、
戦争の表舞台と裏舞台を織り交ぜながら絵巻物のように物語を紡ぐ。
第3部、第1編の1章から23章を大まかに要約すると次のようになる。
第3部、第1編の1章
戦争の原因に関する語り手の批判的考察。
第3部、第1編の2章~7章
6月12日、ネマン川を渡るナポレオンとヴィルナで舞踏会を楽しむアレクサンドル一世が対比的に描かれ、ロシア皇帝の使節バラシェフの見聞を通じて、仏露両皇帝の開戦時の心境が語られる。
第3部、第1編の8章~11章
トルコ戦線経由でドリッサのロシア軍総司令部へ赴いたアンドレイ公爵が、皇帝の大本営における諸派閥の人間模様を観察する。指揮系統を乱す皇帝はこの後、体よく戦争の現場から追い払われる。
第3部、第1編の12章~15章
騎兵大尉となったニコライが7月13日のオストロヴナの戦闘で急襲に成功、勲章を得ながら、敵に加えた己の暴力に嫌悪を覚える。
第3部、第1編の16章~23章
戦争色が強まるモスクワ。聖ペテロ・パウロ祭の祈禱を契機に元気を回復するナターシャ、数秘術の文字計算から黙示録の「獣」たるナポレオンに対抗する使命を自覚するピエール、出征を志願してクレムリンの皇帝来駕歓迎式に出かけるペーチャ、皇帝を迎え熱狂する7月15日の貴族会の様子が語られる。
戦争そのものの描写の部分は、正直、読みづらい。
地名や、次々に出てくる人名や階級などにも馴染みが無く、
読むのも、要約するのも、時間がかかった。
前回、一人読書会『戦争と平和』をアップしたのが1月18日で、
それから随分と時間がかかったのは、それが原因である。
戦争シーンに比して、
ナターシャやピエールが出てくる場面にはホッとさせられる。
特にナターシャのその後が心配だったので、
次第に回復していく過程を読み、胸をなでおろした。
私が最も感情移入できる人物はピエールなので、
ピエールの視点でいつもナターシャを見ている自分がいる。
私もピエールと心境を同じくしており、
ナターシャには幸せになってもらいたいといつも思っている。

今回読んだ部分で、一番印象に残っているのは、
ニコライがオストロヴナの戦闘で急襲に成功、勲章を得ながら、
敵に加えた己の暴力に嫌悪を覚える箇所だ。
聖ゲオルギー十字勲章の授与は、嬉しい驚きであった筈なのに、
精神的な吐き気が去らなかった。
ニコライはどうしても納得のいかないことがあったのだ。
ニコライがずっと考えていたのは自分の輝かしい手柄のことだった。それは驚いたことに聖ゲオルギー十字勲章をもたらし、勇者という評判まで与えてくれた。だが何かしらどうしても納得のいかないことがあったのだ。〈つまり敵も俺たち以上に恐怖心を持っているってことだ!〉彼は思った。〈つまり世にいう英雄的な行為とは、たかがこれっぽちのことだったのか? しかも俺があんなことをしたのは果たして祖国のためだっただろうか? 顎がくぼんで青い目をしたあの男に、いったいどんな罪があるというのか? しかもあの時のあの怯えっぷりはどうだ! あいつは俺に殺されると思ったのだ。なんで俺があいつを殺さなくちゃならない? 俺は手が震えた。なのに聖ゲオルギー十字勲章を頂戴した。何が何だかさっぱり分かりゃしない!〉(139~140頁)
単なる英雄譚にせず、ニコライの葛藤を描くことで、
トルストイは『戦争と平和』をより深みのある作品にしているのだ。
第3部、第2編では、いよいよ戦争が本格化する。
第3部、第2編は39章まであり、かなり長い。
私にとっても長く、苦しい、そして楽しい闘いが続きそうである。(笑)
